ざあざあと降りしきる雨の中、小学生はランドセルを揺らしている。傘を忘れてバス停で雨宿りをしている私には目もくれずに、隣の友人と談笑を繰り広げていて、その笑顔は雨の中でも眩しく見えた。
ああ、私も少し前までそっちに居たのになと、懐かしさと羨望が入り混じった視線を向けている。いや、このまま見続けるのは宜しくない。不審者情報に載って仕舞えば面倒だ。かと言って暇を潰す事が出来ないのも中々に辛い。スマホは事切れてうんとも言わないし、お気に入りの小説は湿気にやられてしまうので鞄から出すのも憚られる。近くで傘を買えばという話なのだが、私の性格上、雨に濡れて傘を買いに行くという行為が本末転倒な気がして受け入れ難い。結果、こうして懐古に浸るだけのどうしようもない男子大学生が生まれてしまった。
駆けるように過ぎていく大学生活に疲れ果て、数週間、いや、もう数ヶ月は経ったか、その程度の歳月を静かに実家で過ごしている。母は何も言わずに受け入れてくれたが、それはきっと、我が身の変わり果てた様を見てしまったからなのだろう。夢を宿した瞳が死に、短く揃えた髪が長く乱雑となり、若々しい顔が澱んだように醜くなったのを見た母の気持ちというのは筆舌に尽くし難いものがあっただろう。
乗りもしないバスが到着する。顔も知らない運転手が扉を閉めるかどうか決めあぐねている。私は搭乗しませんという意を込め、指で✖️字を作った。過ぎ去ったバスが起こす水飛沫が、スニーカーとズボンの裾を濡らしたけれども、今の私には何の感傷も無い。昔ならきっと、不平不満を口にしていたろうが。
「危ない!」
単純明快な一言。声変わり前の、キンと響く声が雨音を裂いて伝わってくる。その警鐘と競う様にゴム製の、青い雨靴が私の懐へと飛び込んできた。
「――本当にすいません! ウチの弟が馬鹿をしてしまって!」
取り敢えず、雨靴で汚れた服の泥を手で払っていると、雨靴より青い顔をして飛び出してきた小学生と、その子に腕を引っ張られた、靴の片方が脱げている小学生とが私の元へとやって来た。二人とも、胸元に付いている名札の名字は同じなので兄弟なのだろう。弟の方は兄と対照的に頬を腫らしているので、十二分に雷を受けたのだろう。であれば、私から何かをする必要はない。
「いや、大丈夫。問題ないよ、どのみちこの雨だもの。はい、雨靴」
ひたすら申し訳なさそうにしている兄へそう伝えつつ、弟の方へ雨靴を返す。少し名残惜しい感触だったが、彼がコロっと嬉しそうな表情になったので、十分だろう。元々彼の物だったのだから。
兄の側はどうしたもんか、更に青ざめている。おおかた、弟が反省の色を見せていない事に対してだろう。これでは再び雷が落ちてしまう、それは良くない。誰かが怒られている場面というのは、第三者にとっても辛いものだ。とにかく私は兄の気を逸らす為、何故雨靴が飛んできたのかを問うた。
「弟は水溜まりで跳ねたり、靴を飛ばして遊ぶことが好きなんです。いつもいつも、人の居る場所では靴を飛ばすなと言っているのですが……」
年長者の苦労というものがよく分かる話だ。溜め息を吐いている彼からは生々しい気苦労が伝わってきて、思わず胃を痛めてしまいそうになる。
もっとも、横槍を入れる様な弟の言葉によって、兄の気苦労は更に加速するのだが。
「まぁ子供というのはそんなもの――」
「ねぇおじさん、どうして雨靴を履いてないの?」
私の濡れたスニーカーを指差して、彼は言った。何故か妙な突っ掛かりを感じ取ったが、その疑問自体は大したものではない。
「ああ、持ってないんだよ。最後に雨靴を履いたのはもう10年近く前だ」
「へー、僕が産まれるより前なんだー」
本当に些末な疑問だったらしく、既に興味が薄れている様子だ。彼にとっては雨靴を当てたことはもう終わったことで、今は暇で暇で仕方ないのだろう。矢継ぎ早に自身の兄へと疑問を投げかけるその姿は微笑ましく思える。
それにしても、子供は疑問を抱きがちで、よく周りを困らせて、大人はよく適当にあしらったり、曖昧な言葉や微笑で濁すのだが、まさか自分が大人の立場になっているとは思わなんだ。
先の疑問のせいか、ふと過去を思い出す。小学生の頃、近くのショッピングモールの靴売り場には色とりどりの大小様々なゴム製の雨靴が押し並べられていて、私は迷わず青色を手にしたことをよく覚えている。今はもう無いショッピングモールでの話だ。だけどそれだけ、中学生になってからは不思議と雨靴を履かなくなってしまい、存在そのものを忘れてしまった。
何故雨靴を履かなくなったのか。その妙な突っ掛かりが気になって随分考え込んでしまう。嘗て哲学書を読み漁った頃のように思考を張り巡らせる。
ああ、なるほど。そんなことだったのかと、合点がいくと思わず笑ってしまう。目の前の二人が怪訝な表情をするのも無理はない。だけれど、今は気分が昂っている。
「ねえ、服が汚れた件についてなんだけど、代わりに僕のちょっとした独り言を聴いてもらうっていうのはどうかな」
我ながら酷い提案。下校中の小学生を引き留めて自論を述べるなんぞ、ソクラテスやデカルトだってそんなことをしないだろう。まさに不審者極まりないが、二人は二つ返事をしてくれた。
私は鞄からペットボトルのお茶を取り出して一口飲む。そして、息を整え語り始めた。
「思うに、私にとってそれは、子供の頃の思い出なんだろう。私も昔は雨の日に心を躍らせたし、通学路を歩きながら遊んだこともあった。でもね、少しずつ歳を取るたびに、そういった楽しさが喪われていくんだよ。代わりに、将来への不安や移り変わっていく環境、人間関係といった物事で埋め尽くされていくんだ。大学生にもなると、路端の石ころを蹴り飛ばすこともしなくなる。日常というものに、新鮮さを感じなくなるんだよ」
そこまで口にして、弟がつまらなそうにしていることに気付いた。それもそうだろう、結局のところこれは自己満足のようなものなのだから。そうして、やっぱり取り止めようかと思ったのだが、兄の方が真剣に聴いていたのでこれでは辞められない。後で弟君に分かりやすく教えてあげてねと伝えて、私は続きを話すことにした。
「だからこそ、『雨靴は小学生の特権』なんだよ。雨靴は、自由で無邪気で、何にでも楽しさを見出せた頃の象徴。私を含め、皆そうではなくなってしまうから、自然と忘れてしまう。それに、雨靴を履いていると否が応でも楽しかったあの頃を思い出す。ふとした瞬間に現れるその過去は、現在が辛ければ辛いほど理想郷となっていく。そんな過去に少しでも懐古してしまうと、あの頃に帰りたいと願って生きていくことになる。それは何よりも悲しいことなんだ、過去に希望を抱いたところで叶うことはないのだから……」
長くなって申し訳ないと言って締め括る。酷い自己満足だが、兄の方は何か学びを得たようでしきりに言葉を繰り返していた。
放課後も随分経って、通学路のランドセルは殆ど見えなくなっている。これ以上二人を此処に留めておくのは良くないので帰宅を促そうとしたのだが、それを遮るかのように着信音が響いた。
「龍樹兄ちゃん、陽斗兄ちゃんから電話!」
「マジか、スマホ貸してくれ!」
兄――龍樹はようやく明るい表情を見せた。弟の方も顔を綻ばせているので、陽斗という人物はかなり弟達に好かれているようだ。
陽斗、という名前には聴き馴染みがある。小学生の頃、毎日のように遊んだ親友の名前が陽斗だった。彼とは進学先の中学校が異なり、中学生になってからは殆ど会う事が無くなってしまった。年に一度は会いに来てくれたが、それも中学三年生にもなると来なくなり、もう6年は顔を合わせていない。当時は自分用の携帯電話を持っていなかったという事もあり、連絡先も分からずじまいだった。
確か、名字は。
「そうだ……名字は……『葦原』……!」
「どうしたのおじさん? 葦原って僕達の名字だよ」
彼は『葦原 陽斗』。目の前にいる兄弟の名字は葦原、その電話相手の兄の名前は陽斗。つまり、あの電話相手は『葦原 陽斗』という名前であり、かつての親友と同姓同名である。
それに気付いた時、私はハッと息を呑んだ。まさか、もしかしたら、そんな言葉がぐるぐると頭の中で巡る。鼓動が早くなって、瞳孔が開く。何度も希い望んだ、理想郷の住人が手の届く場所に居る。
だが同時に、それを否定するような気持ちが湧いてきた。もし彼と話せば、間違いなく自分の中にいる彼は死ぬだろう。なにせ6年の歳月が経ったのだ、それだけの期間があれば人というのはがらりと変わる。例えるなら、迅坊っちゃんと閏土の関係のように。そう、私にとっての閏土は陽斗なのだ。
そうこうしていると龍樹君がスマホをこちらへ渡してきた。どうしてだと聞くと、向こうが話をしたいと言ったらしい。そして断れないまま、私はスマホを耳に近付ける。
「お電話代わりました……。えっと、服の代金とかは必要無いですよ、その、陽斗、さん……」
緊張して舌が回らない。酸素が脳に回っていないせいか、頭の中が真っ白だ。何を喋ったのかすら自分でも分からない。目の前が朧げになっている。
何かあったのか、通話相手は口を閉ざしてしまう。もしや失礼をしてしまったのだろうかと、頭を抱えた。
不意に、懐かしい声が聴こえる。
「――久しぶり。駿坊っちゃん、なんてな」
雨の音は、もう聞こえない。
「龍樹兄ちゃん! 晴れになったよ!」
「おー、雨雲が遠くに行ったなぁ」
それでも何故か、頬が濡れるのは何故だろう?
雨宿りをしている筈なのに。
「そのあだ名、覚えてたんだ……てっきり何もかも忘れてたのかと……」
「忘れる訳ないだろ。確かにここ数年めっきり会わなくなったが、だからといって忘れたわけじゃないし、お前を小学生の頃友達だった奴、だなんて思ってないからな。現在でも俺とお前は友達だ」
あの頃の面影を残した明朗快活とした声。私のなんと愚かなことか、彼は今でも私を友と呼んでくれた。ただそのことが嬉しくて、とめどなく喜びが溢れてくる。
「ひとまず、うちの弟が馬鹿やらかして申し訳ない。本来なら弁償をした方が良いんだが、本当にいいのか?」
「ああ、いいんだ。もう晴れたから」
それから、陽斗と暫く談笑をしていたが、これ以上二人の兄弟の帰宅が遅くなるといよいよ迷惑になってしまうので、名残惜しいけれどこれ以上は通話できない。
「なぁ、本当にこの後会わないのか? 折角の機会だ、色々話したかったんだが」
「いいんだ、電話番号も教えてくれたし。今の私はまだ君と会うのに相応しくない。また今度、晴れの日にドライブでもしよう」
「そうだな。次会った時は! また、一緒に遊ぼう」
「ああ。また、昔みたいに」
電話を切ると、スマホを龍樹へと返す。二人は頭を下げると仲良く二人で帰って行った。そういえば、最後まで弟の名前を知ることはなかったが、次会う時に教えてもらわなければならない。彼は大切な事を教えてくれたのだから。
そういえば去り際に一言、言葉を残していった。
「おじさん。雨靴じゃなくても、水溜まりで遊べるよ」
私の自論を踏まえた言葉だったのかどうかは分からないが、少なくとも彼のお陰で心の突っ掛かりが取れたことは確かである。
さて、私もいよいよバス停に留まっている理由が無くなったので、実家へ帰ることにしよう。そう、路端の石ころを蹴飛ばしながら――。
帰路、私は希望というものについて考える。結局のところ私の抱いていた理想郷というのは、ハリボテの空想に過ぎない偶像だった。つまり、希望というのは絶望と隣り合わせであり、それはある種の病だということではないか、ということだ。私は考えた――過去へ希望を持つというのは、多くの人が歩んで作った道を進むといえば聞こえが良い。しかし、その道は多くの人が既に通り過ぎた道であり、それがいかなる大通りであったとて廃道なのだ。どんな道であれ、その先に希望があるのではなく、希望の先に道ができるのだ。その認識の違いが、絶望と希望を隔てるのだろう。


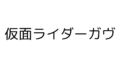
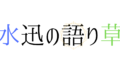
コメント